高校の少林寺拳法部にいたとき、毎日先生がお話をしてくれた。
同じ話を何回もすることもあれば、当時は分からなかったが、後の人生で役立つ話をたくさんしてくれた。
その中でも、覚えているのは「脳みそをスポンジにしろ」という話だ。
何の話から、その話になったかは覚えていない。しかし先生の言いたかったことはこうだ。
最初から、物事を判断するときに「これはいい、身に着けよう」とか「これはいらん」とか考えるな。
まずは、素直に脳みそをスポンジにしていったん吸収しなさい。そして自分で考えて、いらんものは捨てろ。
当時はぽかっと聞いていたが、この話は深く残っている。
僕はこれを「脳みそスポンジ理論」と名付けた。
少林寺拳法の現場で必要とされる脳みそスポンジ理論
幸い、自分はこのことを肝に銘じて生きてきた。
少林寺拳法の世界では、特に大事にしている。
実際、高校卒業して28年ぶりに再開した少林寺拳法は、当時知らなかったいろんなことにぶつかった。
例えば鈎手1つでも、僕らのときは五指を張りあいてに向けるような鈎手だったが、今やると「昭和や」と言われる(笑
その他いろんなことに違和感はあったが、そこは師の教えである脳みそスポンジ理論で、とりあえず言われたとおりにやってみるのである。
他拳士の技術を否定する指導者
僕は高校時代、部活の中での少林寺拳法しか知らなかった。
そして、復帰するとまあいろんな型でやる先生方がいるものだと驚いた。
考えてみれば、元気と勢いのある高校生がする技と、高齢になってくる技は変わってくる。
また、体格差、修練の度合いによっても違う。
しかし、その中で悲しい場面に出くわすこともあった。
例えばAという先生がみんなの前で、技を披露し、それを教えていた。
生徒側の後ろにいたB先生が「あんな技使えんやろ」というのが普通に聞こえていた。
そもそも、同じ指導者の立場として、生徒の前にいうことではない。
もっと言うと、B先生には伸びしろが無いのだ。
なぜなら、否定をした瞬間、脳みそはスポンジではなく石になる。
なんにも吸収しない。
もし、自分の理論と違うと思っても、その違いから学べることがあるのだ。
田中先生はワシの技なんかやらんでええでしょ
と言うことで、僕は出来る限りいろんな人の少林寺拳法を学びたいと思っている。
そもそも少林寺拳法の成り立ちが「ハイブリッド」である。
だから、僕は自分の技術にプライドを持てるように学ぶが、執着はしないようにしている。
ある時、小柄な先生が担当として教えてくれていた。
各自練習の際に、先生に質問をして教えてもらうおうとした。
小柄な先生は、僕が大柄なので「田中先生はワシの技なんかやらんでええでしょ」と笑いながら言われた。
僕は「そんなん、言わないでください。であれば、僕が先生の技術ができれば無敵じゃないですか」と返して、教えてもらった。
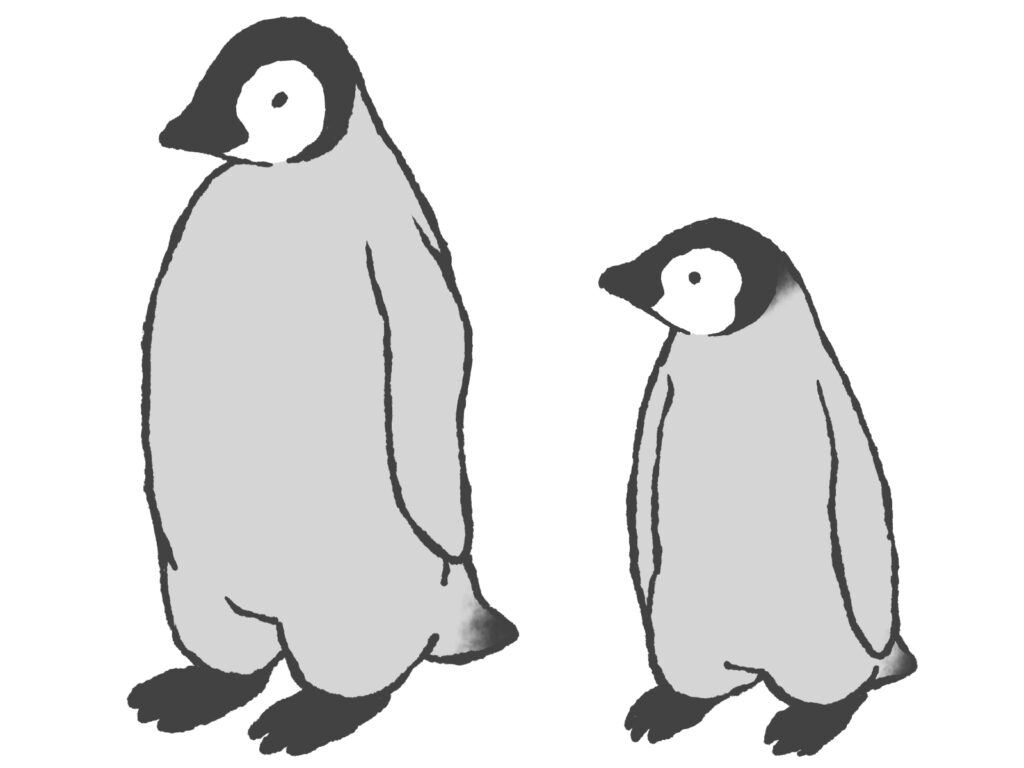
少林寺拳法の技術こそ多様性
少林寺拳法の技術こそ、まさに今言われる多様性だ。
180センチ体重90キロ50歳の僕と、160センチ満たない50キロ未満の高校生女子では違って当然。
変えていけない法形の原則は別だが、ほかは他の人のやっていることを見て「盗めるところ盗むべき」だろう。
これは少林寺だけでなく、他武道に対してもだ。
合気道が使えない。果たしてそうだろうか?実際体験してみると恐ろしい技術であり、そこから学ぶことは山ほどあった。
当てない伝統空手は弱い。今総合格闘技で活躍している選手は、伝統派空手の動きをうまく活用している。
フルコン空手は顔面ないやん。たしかに無いが、あのローキックをや鎖骨打ちは脅威だ。
脳みそをスポンジにして、いろんなことをまずは吸収し、そこから取捨選択すればいい。
武道の上達に「これでなくてはいけない」は邪魔でしかないと考える。
